夕焼けに 唐紅の 初氷
小林一茶
冬の澄み渡った夕焼け空は、それは見事なグラデーションを描きます。そして今日もまた、美しい夕焼けに照らされながら、カラスたちがあちらのほうからもこちらのほうからも次々とねぐらへと羽ばたいて行く様子が見えます。それにしても、カラスたちにとってねぐらに帰り、たくさんの仲間たちと過ごす時間は、果たして安息の時間なのでしょうか、はたまた不安な時間なのでしょうか。
「妣が国」という言葉があります。民俗学者の折口信夫が丁寧にその意味を歴史的に紐解いていることで有名ですが、それによれば、今のこの世界とは別の世界のことを「妣が国」と呼ぶそうです。異国であり他国のことを「妣(はは)」と関係づけるのは、嫁いできた母のふる里は異国(かつて自分の住む村や集落の外は異国でした)であり、亡き母(妣)の魂の還る場所(母のふる里)を「妣が国」と呼ぶようになったことに由来していると言います。この言葉の由来からは、かつて結婚すること(女が妻となり母となること)には今生の別れにも匹敵するような覚悟を必要としていたことをも示しているように思えます。
わが国日本では伝統的に不安や恐怖といった感情と関わる場所や物に、不思議と紅色が使われています。神社の鳥居の色、ダルマの色、鬼の色など。なかでも古くは日本書紀の記録にも見られると言われる「疱瘡絵」の紅色は注目に値します。疱瘡絵とは、日本で天然痘が大流行した際、病者の回復を祈願して見舞いとして送られたもので、主に朱墨で描かれた絵のことを指します。そして興味深い点は、この紅色は天然痘の痘痕の色を表していたとされている点です。つまり、恐ろしい病の表れである痘痕の紅色を、見ないように視界の外に排除してしまうのではなく、わざわざその色を使って病気平癒の祈願を行っているわけです。鳥居やダルマなどの紅色にも同じ意味が込められています。不吉と吉の間合いを彩る色。それが紅色です。
異国やあの世のことを「妣が国」と呼ぶ感性は、この紅色に対するわたしたちの感性と共通した心の働きがあります。不安や恐怖を呼び起こす異国や死の世界という最も遠い場所を、忌み嫌って遠ざけようとするのではなく、本来最も身近にあって心の拠り所にもなる「母」と関係づけようとする、高度で複雑な心の働きが。それは、安心と不安の間合いを「母」でつなぎ合わせようとする心の働きだと言い換えてもよいでしょう。
昼(光の世界)と夜(闇の世界)の間合いに立ち現れる夕焼けの紅に、「唐紅(異国から訪れた紅色)」を見た一茶の感性にも、おそらくは同じ心の働きが作動していたように思えます。
畠山正文
参考文献
折口信夫 『妣が国へ・常世へ 異郷意識の起伏』 青空文庫 (折口信夫 妣が国へ・常世へ 異郷意識の起伏 (aozora.gr.jp))
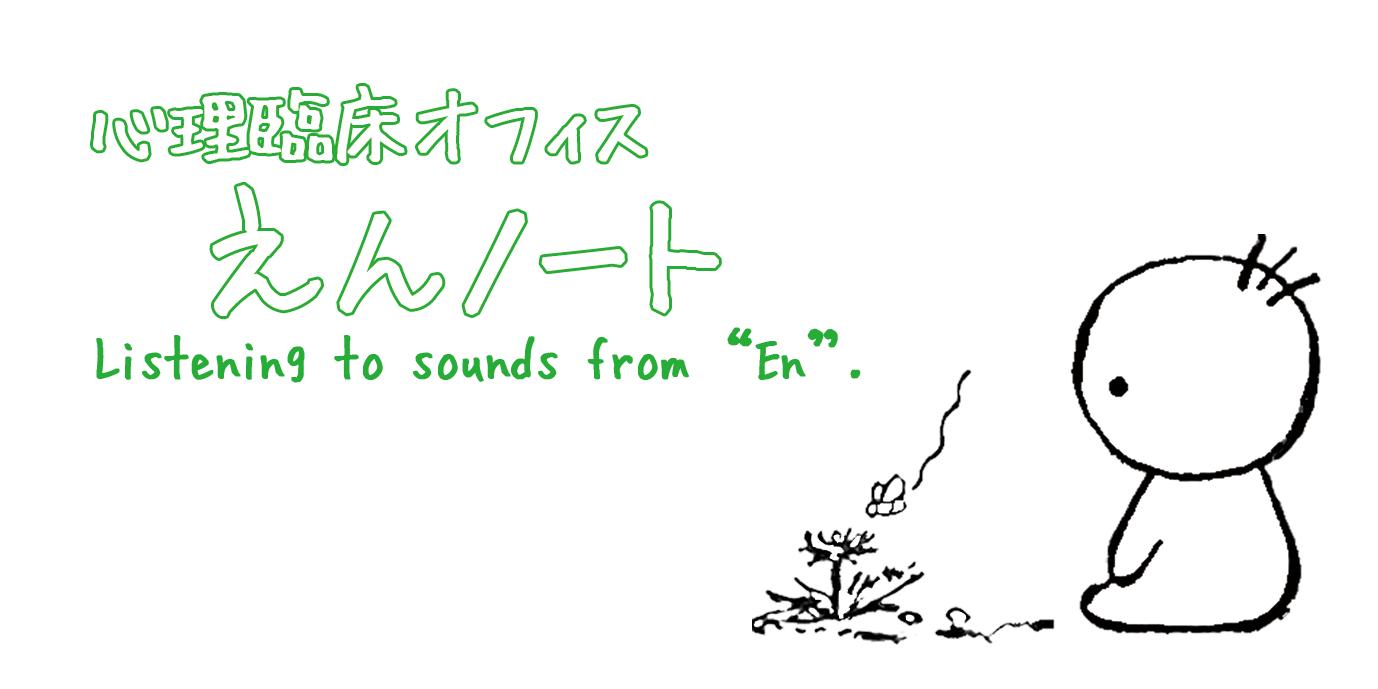

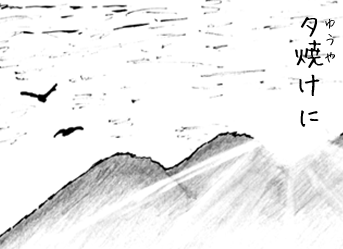




コメント