古郷やよるも障るも茨の花
小林一茶
椋鳥(ムクドリ)という鳥をご存じでしょうか。夕方になるとものすごい数の椋鳥の群れが、キュルキュルと大きな鳴き声を上げながら、ねぐらである街の電線や街路樹に集まってきます。鳴き声の大きさやフン害から、街で暮らす人々にとって、この椋鳥たちの群れは、一般的には迷惑であまり良い印象ではないのでしょう。
江戸時代、交通網が整備されていくにつれ、信濃(現在の長野県)の貧しい農民たちの多くが、冬になると遠路はるばる江戸の町に赴き、日銭を稼ぐ日々を過ごすようになりました。この信濃からの出稼ぎ者のことを、江戸の人々は、集団でやってきては町に迷惑をまき散らすという侮蔑的な意味で「椋鳥」と呼びました。
比較的豊かな暮らしの農家出身の小林一茶は、長男であったにもかかわらず、継母との折り合いが悪いという理由で、江戸に奉公に出されます。しかし、そんな事情を詳しく知らない江戸の人々は、一茶もまた同じ「椋鳥」として扱います。実母の死、継母との確執、父に捨てられた寂しさ、江戸の人たちからの侮蔑的な扱い…このような経験もまた、一茶にとっての「故郷」が「茨の花」へと変わっていくきっかけになったのではないか、と思います。
14年ぶりに故郷に帰郷してから間もなく詠んだ句が、今回取り上げた句です。
古郷やよるも障るも茨の花
帰郷しても、故郷は彼を温かく迎え入れてはくれませんでした。長男でありながら郷を捨てた不届き者という誹りを受けたり、相変わらず継母との関係は悪く、また帰郷後すぐに実父は重病に臥せって亡くなってしまいます。
この句には、そんな故郷に対する、一茶の複雑な心境が見事に現れています。実母を失い、父から捨てられ、継母に嫌われ、父を失うといった、たくさんの「茨」を持った場であると同時に、それでもやはり美しい「花」でもあるのが、一茶にとっての「故郷」です。
わたしたち一人ひとりの「わが心」もまた、一茶にとっての「故郷」と同じように、独特の複雑さを持っています。わたしたちにとって「わが心」は、知れば知るほど、不思議で複雑で奇妙です。見捨てられたり、追い出されたり、憎んだり、見失ったり、それでも愛おしく感じたり・・・まさに、「茨の花」としての「わが心」。一茶にとっての「故郷」が、遠く江戸への流浪を通じて、かけがえのない「茨の花」となり得たように、わたしたちにとっての「わが心」もまた、それがかけがえのない「茨の花」であることを悟るには、ひょっとすると流浪の時間が必要なのかもしれません。
畠山正文
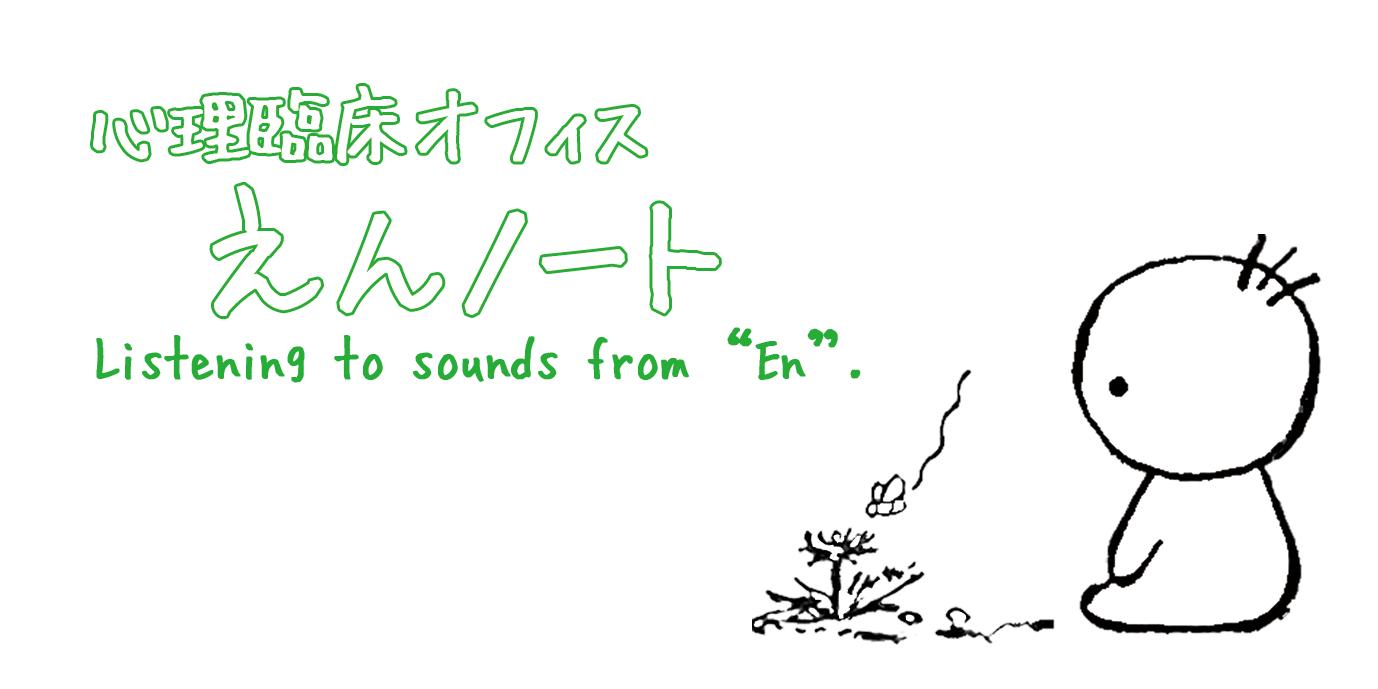
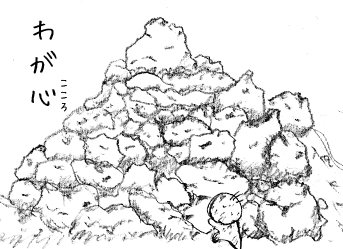


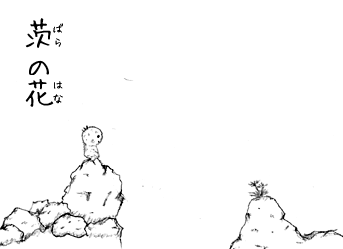

コメント